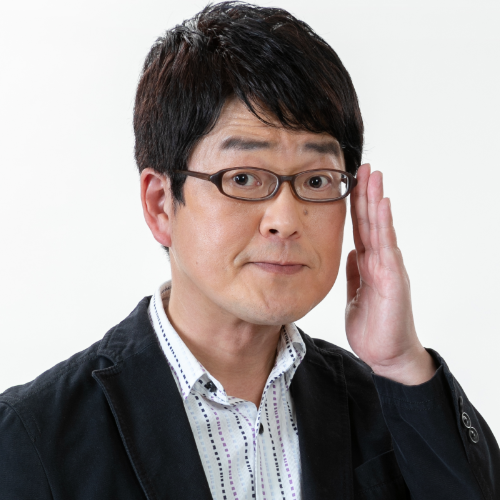2024.01.23
Chiba Prefecture, attractive and my hometown 2-1
『ゴジてれChu!』第1部で、きょうは千葉の魅力を特集しました。去年に続き、2回目の担当(去年の成田山に名物鰻・ひこうきの見える丘・小江戸佐原の魅力は、こちらをクリック)です。年に2度、石井アナと交互に担当しているのですが、理由は千葉が故郷だから。
という事で、今回は旧下総国(しもうさのくに)の香取(かとり)市、香取郡の多古町(たこまち)、香取郡に隣接する銚子(ちょうし)市を巡ってきました。そのこぼれ話です。
という事で、今回は旧下総国(しもうさのくに)の香取(かとり)市、香取郡の多古町(たこまち)、香取郡に隣接する銚子(ちょうし)市を巡ってきました。そのこぼれ話です。
 後ろに見えますのが、銚子電鉄で御座います! |
 タコスを食す。その理由は…(その5で) |
朝4時に郡山をロケ車で出発、最初に向かったのは香取市にある「香取神宮」です。ただ神宮にお邪魔する前に、利根川沿いに建つ鳥居の撮影からです。
「鳥居河岸(とりいがし)」若しくは「津宮浜鳥居(つのみやはまとりい)」と呼ばれるこの鳥居は、香取神宮の御祭神「経津主大神(ふつぬしのおおかみ)」が海路を経てここから上陸されたと伝わる場所に建てられています。
「鳥居河岸(とりいがし)」若しくは「津宮浜鳥居(つのみやはまとりい)」と呼ばれるこの鳥居は、香取神宮の御祭神「経津主大神(ふつぬしのおおかみ)」が海路を経てここから上陸されたと伝わる場所に建てられています。
 川の土手の向こうに、鳥居の上の部分が顔を出す。 |
 こちらが利根川沿いに建つ鳥居河岸。江戸時代は舟で来て、鳥居をくぐって参拝したとか。 |
因みに経津主大神は、出雲の国譲りの神話で、大国主命(おおくにぬしのみこと)から日本を譲り受けた神の一柱と伝えられています。鳥居は高さが約9mあるそうで、土手から日が昇ってくる様子は神々しくさえ感じられました。
 大きな鳥居に、カメラマンが小さく見える。 |
 土手の向こうから朝日が昇る。 |
利根川側から一ノ鳥居でもある鳥居河岸を潜ると、土手には常夜灯があり、香取神宮への旧参道が続きます。
香取神宮は神武天皇の御代(詰まり紀元前)に建立されたと言われているほど歴史は古く、明治以前に「神宮」と呼ばれるのは伊勢神宮、香取神宮、茨城県の鹿島神宮のみと言われる程、格式の高い神社です(地元の人の前で「神社」と言うと、注意される場合も。それ位、地元の人には香取「神宮」の呼び名で通っている)。
香取神宮は神武天皇の御代(詰まり紀元前)に建立されたと言われているほど歴史は古く、明治以前に「神宮」と呼ばれるのは伊勢神宮、香取神宮、茨城県の鹿島神宮のみと言われる程、格式の高い神社です(地元の人の前で「神社」と言うと、注意される場合も。それ位、地元の人には香取「神宮」の呼び名で通っている)。
 それでは香取神宮に向かいましょう! |
 鳥居の先の土手には、常夜灯が。 |
鳥居河岸から2~3㎞進むと、参道へと続く道が見えます。早速美味しそうなものが店先に並びますが、まずは参拝を済ませてから…。
茶店等が続く道を進むと、朱塗りの大鳥居が見えてきます。
茶店等が続く道を進むと、朱塗りの大鳥居が見えてきます。
 いよいよ香取神宮の参道へ(バスでも来られる)。 |
 朱塗りの大鳥居。ここに移って100年も経っていない(後述)。 |
更に多くの石灯籠に囲まれた通称「表参道」を進みます。石灯籠には「春日大社の鹿、三笠山、炎の3つを象るものが多い」のだそうです。因みに鹿は、春日大社同様神の使いです。
 石灯籠と木立に挟まれるように参道が続く。 |
 春日大社の鹿などをかたどったデザインの石灯籠が多い。 |
その表参道を左に折れて見えてくるのが、通称「石の鳥居」と総門です。ここからは神宮の権禰宜に案内して頂きます。
総門をくぐると右に折れて更に大きな「楼門」があります。
総門をくぐると右に折れて更に大きな「楼門」があります。
 石の鳥居。一ノ鳥居同様、特に彩色はされていない。 |
 奥に見えるのが総門。 |
「この楼門は元禄13(1700)年に造営されました。額の『香取神宮』の文字は、東郷平八郎による揮毫です。」
額をよく見ると、左に東郷平八郎の名前が辛うじて見えます(目が悪いので)。因みに茨城県の鹿島神宮の名も、東郷平八郎によって書かれた文字が使われているそうです。
額をよく見ると、左に東郷平八郎の名前が辛うじて見えます(目が悪いので)。因みに茨城県の鹿島神宮の名も、東郷平八郎によって書かれた文字が使われているそうです。
 造られて320年以上経つ楼門。朱塗りが目に眩しい。 |
 額は東郷平八郎の筆。 |
総門も楼門も朱塗りで、日光東照宮でも見られるような色合いですが…
「造営は徳川五代将軍綱吉の命によるものですから、日光東照宮の影響も受けているのでしょう。」
そして総門と楼門の間、一度右に曲がって左に楼門が見えるのですが、これは理由があるのですか?
「いえ、元々総門をくぐって右に曲がったこの道が旧参道なんです。鳥居河岸に繋がる道ですよ。」
「造営は徳川五代将軍綱吉の命によるものですから、日光東照宮の影響も受けているのでしょう。」
そして総門と楼門の間、一度右に曲がって左に楼門が見えるのですが、これは理由があるのですか?
「いえ、元々総門をくぐって右に曲がったこの道が旧参道なんです。鳥居河岸に繋がる道ですよ。」
 楼門を裏から。狛犬が門を守っている。 |
 楼門から拝殿を望む。こちらは黒漆ぬりの建物だ。 |
そして楼門の奥に見えたのが拝殿です。
「拝殿は皇紀2000年(昭和15年・1940年)の奉祝で建てられたものです。」
それまでは拝殿右手にある現在の神楽殿が拝殿だったそう。檜皮葺で、白木のままではなく、黒の漆塗りというのが特徴的です。
「塗った直後は漆器のような光沢もあったんですよ。日の当たる加減で、今の色になっています。」
関東を中心に約400社ある香取神社の総本社だそうですが、どんな願いをする方が訪れるのでしょう?
「武の神様なので、武道やスポーツに励んでいる方や勝負事をする方、仕事で何かに挑戦する方等の参拝が多いようです。」
今年は三が日で40万から50万人が訪れたそうで、
「概ねコロナ禍前位まで戻ってきました。」
そしてその奥にあるのが本殿(1700年造営)です。
「拝殿は皇紀2000年(昭和15年・1940年)の奉祝で建てられたものです。」
それまでは拝殿右手にある現在の神楽殿が拝殿だったそう。檜皮葺で、白木のままではなく、黒の漆塗りというのが特徴的です。
「塗った直後は漆器のような光沢もあったんですよ。日の当たる加減で、今の色になっています。」
関東を中心に約400社ある香取神社の総本社だそうですが、どんな願いをする方が訪れるのでしょう?
「武の神様なので、武道やスポーツに励んでいる方や勝負事をする方、仕事で何かに挑戦する方等の参拝が多いようです。」
今年は三が日で40万から50万人が訪れたそうで、
「概ねコロナ禍前位まで戻ってきました。」
そしてその奥にあるのが本殿(1700年造営)です。
 本殿(左)と拝殿(右)。 |
 本殿も楼門と同じ年に造られた。 |
そしてその拝殿・本殿の脇には「三本杉」があります。
「三本の杉のように見えますが、実は一つの株から幹が3つに分かれたと言われています。ただ真ん中の杉は現在うろだけになってしまいました。」
「三本の杉のように見えますが、実は一つの株から幹が3つに分かれたと言われています。ただ真ん中の杉は現在うろだけになってしまいました。」
 三本杉を眺める。実は株は一つ。 |
 真ん中の杉は、うろの部分だけが残る。 |
一方、脇の2本は樹勢もあってパワーを感じます。左の杉にワイヤーが巻き付けてあるのは、「暴風などで本殿に倒れないようにする」為のもので、基本は自立している三本杉です。
「周りには杉が多いので、春は廊下や壁がスギ花粉でびっしりになります。雑巾がけした所とそうでない所がはっきり分かる位ですよ。」
15の春から花粉症の私は、ロケが2月~4月でなくて良かったと心から思ったのでした。
「周りには杉が多いので、春は廊下や壁がスギ花粉でびっしりになります。雑巾がけした所とそうでない所がはっきり分かる位ですよ。」
15の春から花粉症の私は、ロケが2月~4月でなくて良かったと心から思ったのでした。
 向かって左の杉。斜めだが空に勢いよく伸びている。 |
 このほかにも杉が社殿を囲む。 |
そして神社…いや神宮に訪れたからには、おみくじを引きましょう。
前回の千葉ロケで、成田山新勝寺で引いたおみくじは…(詳しくは、こちらをクリック)でしたが、先程拝殿でお参りも済ませましたし、果たしておみくじの結果は?
吉でした。ほっとすると同時に、今年「ぶらカメ」で訪れた大山祇神社では中吉を引いたので、一つランクアップ?(おみくじは大吉の次に良いのが、中吉ではなく吉だという説があるのです)。大山祇神社の御利益でしょうか? 結んでも持って帰っても良いと言われたので、今回は持って帰りました。
前回の千葉ロケで、成田山新勝寺で引いたおみくじは…(詳しくは、こちらをクリック)でしたが、先程拝殿でお参りも済ませましたし、果たしておみくじの結果は?
吉でした。ほっとすると同時に、今年「ぶらカメ」で訪れた大山祇神社では中吉を引いたので、一つランクアップ?(おみくじは大吉の次に良いのが、中吉ではなく吉だという説があるのです)。大山祇神社の御利益でしょうか? 結んでも持って帰っても良いと言われたので、今回は持って帰りました。
 おみくじを引いてみる。 |
 吉でした♪ 私は持ち帰ったが、結べる場所もある。 |
その後、御祭神がもう1か所祀られているという「奥宮(おくのみや)」へ権禰宜に案内して頂きます。楼門を出て右に折れ、左の総門をくぐらず真っすぐ進みます。
「これが旧参道でした。皇紀2000年を機に、この道の先にあった朱塗りの鳥居を現在の位置に移しました。いまの参道は嘗ては周りが田んぼで、こちらの旧参道沿いに茶店や旅館などが並んでいました。」
明治天皇がいらした時も、この旧参道を二頭立ての馬車で通られたそうです。
「これが旧参道でした。皇紀2000年を機に、この道の先にあった朱塗りの鳥居を現在の位置に移しました。いまの参道は嘗ては周りが田んぼで、こちらの旧参道沿いに茶店や旅館などが並んでいました。」
明治天皇がいらした時も、この旧参道を二頭立ての馬車で通られたそうです。
 こちらが旧参道(神宮方向を望む)。左手には今も旅館が残っている。 |
 神宮を背にして旧参道左手に、奥宮がある。 |
奥宮はその名の通り、神宮の中でも旧参道の途中にひっそりと佇んでいます。
「同じ神(経津主大神)を祀っているんですが、落ち着いた神と荒ぶる神と、2つを祀る事で、丁重に祀る意味合いがあります。」
鳥居をくぐると奥宮への道は木や竹に覆われ、森の中を歩いているかのようです。こちらは質素な感じで、朱も黒漆もなく、素材の色がそのまま活かされた小さな社殿で、51年前の伊勢神宮のご遷宮の際に出た古材で造られたそう。
「お参りする際は両方行かれる事をお勧めします。」
「同じ神(経津主大神)を祀っているんですが、落ち着いた神と荒ぶる神と、2つを祀る事で、丁重に祀る意味合いがあります。」
鳥居をくぐると奥宮への道は木や竹に覆われ、森の中を歩いているかのようです。こちらは質素な感じで、朱も黒漆もなく、素材の色がそのまま活かされた小さな社殿で、51年前の伊勢神宮のご遷宮の際に出た古材で造られたそう。
「お参りする際は両方行かれる事をお勧めします。」
 奥宮の入口。 |
 木立からは木漏れ日も少ない。 |
千葉のパワースポットの1つ、香取神宮は、JR成田線の佐原(さわら)駅からタクシーで約10分、またバスでも来る事が出来ます(バスは時間と本数に要注意)。香取(かとり)駅の方が距離的には近いそうですが、香取駅からだと徒歩しか手段が無いそうです。香取神宮では朝8時半から夕方5時の間だと、お守りやお札、御朱印などを手に入れる事が出来るそうです。(つづく)
 JR佐原駅。駅前にはバスやタクシー乗り場もある。 |
 佐原駅にはJR成田線で来られる。 |
ここまでは香取神宮の真面目な話をお伝えしました。今度は朱塗りの鳥居前に並んでいたお店で、食べて“厄”を落としましょう⁉
その2「香取神宮前で、縁起の良い団子&いもコロッケ なぜコロッケなのに“いも”と強調?」は、こちらをクリック。
その2「香取神宮前で、縁起の良い団子&いもコロッケ なぜコロッケなのに“いも”と強調?」は、こちらをクリック。
 こちらが縁起の良い団子? |
 コロッケに「いも」とわざわざ付けるのには理由が…。 |
全文を読む