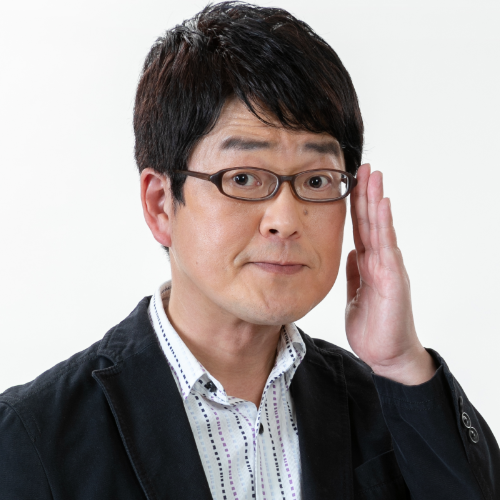2021.01.14
with a camera in Kawamata Town 2-1
『ゴジてれChu!』木曜恒例「ぶらカメ」のコーナー、今回は川俣町(かわまたまち)に行ってまいりました。このコーナーで川俣町を訪れるのは、私としては2回目です(1回目の様子は2019年8月29日・28日・27日のブログをご覧ください)。そのこぼれ話です。
 朝一番の散歩者は、動物? |
川俣町は県北にある人口1万2千人余り、127.7平方kmの広さの町で、昔から養蚕・絹織物の生産が盛んな町でした。往時ほど盛んではありませんが、絹織物は依然として生産が続いているほか、国内最大の中南米音楽祭「コスキン・エン・ハポン」の開催や、川俣シャモの産地としても有名です。
 川俣町を見下ろす。奥には雪をかぶった吾妻連峰や吾妻小富士が見える。 |
ただこの日は太陽が昇っても氷点下5度以下という土曜の午前8時過ぎ、車の往来はあっても、歩いて行き来する人の姿はまず見られません。
 朝日は昇るが、気温が上がらない…。 |
結構長い間ぷらぷら歩いていると、地元スーパー「えびすや川俣町店」の店員さんが、入口の買い物かごをアルコールスプレーで消毒している姿を見かけました。9時の開店を前に、準備をしている最中です。
「お勧めは、野菜やお惣菜です。」
「お勧めは、野菜やお惣菜です。」
 川俣町民の台所を支えるスーパー「えびすや」。 |
最近は新型コロナウイルスの影響で家庭で料理を作る機会が増えたせいか、生鮮食品が以前より売れるようです。寒さで甘くなるキャベツは山形産ですが、これは雪が深い日本海側のものが先に出回っている為のようで、
 寒い時期のキャベツは、甘くなって更に美味しい。 |
「福島産の寒中キャベツはこれからですね。」
との事でした。またお惣菜は自家製で、昔からよく作っているとの事です。取材の許可を店長に得ます。
との事でした。またお惣菜は自家製で、昔からよく作っているとの事です。取材の許可を店長に得ます。
 朝からお惣菜、お弁当作りが進む。美味しそう~♪ |
「うちは30年以上になります。福島市飯野に本店があって、ここが2店舗目です。元日以外は営業していますよ。」
ここ川俣町にある所謂スーパーは2店舗。町民の台所を支える店の一つです。
(後日視聴者の方から、4店舗では?とご指摘を頂きました。失礼しました。)
ここ川俣町にある所謂スーパーは2店舗。町民の台所を支える店の一つです。
(後日視聴者の方から、4店舗では?とご指摘を頂きました。失礼しました。)
 「定休日は元日だけなんです。」と店長。 |
因みにこちらは社長で、お兄さん。お父様が会長だそうです。
 福島市に1号店を構える。社長は、店長のお兄さんです。 |
「うちは『おこわ』を昔から出しています。この辺りでは人が集まる時におこわを出す機会もあるので、予約を受けて仕出しをする事もあります。」
おこわは2種類。早速試食してみます。
おこわは2種類。早速試食してみます。
 開店から並んだおこわ。これが人気だと言う。 |
「甘豆ふかし」は、甘く煮た金時豆を使っています。その甘みがおこわにも染みて、優しい甘さで包まれます。「五目おこわ」は椎茸・人参・蒟蒻・牛蒡等を醤油ベースで味付けしたものが入っていて、両方セットで頂くと、双方の美味しさが引き立ちます。おにぎりと違ってふわっとラップで包んであるだけなので、蒸したおこわの食感自体も楽しめます。
 おこわを頂く機会が多い地域柄。仕出しも請け負う。 |
「(2種類で)100個作りますが、結構早くに売り切れますね。」
との事。そのほかにもお惣菜・お弁当なども作っていて、朝から次々と店頭に並んでいきます。自家製というのが、また好いですね。
との事。そのほかにもお惣菜・お弁当なども作っていて、朝から次々と店頭に並んでいきます。自家製というのが、また好いですね。
 朝からお年を召した方がお弁当を買っていく姿も見られた。 |
さて同じ通りを歩いていると、蔵構えの立派なお宅があります。もしかしてお宝が眠っていたりして…。通りに面した所はガラス戸になっていますが…今はここから入る感じではなさそうです。玄関を探します。ご主人が対応して下さったのですが、ご本人は出演NG。ですが、
「蔵の中を写す分にはどうぞ。」
と仰って下さり、蔵の中へ特別に通して頂きました。すると…
「蔵の中を写す分にはどうぞ。」
と仰って下さり、蔵の中へ特別に通して頂きました。すると…
 立派な蔵(兼住宅?)が建つ。 |
通りに面した側には、机のようなものやペダル、ハンドルのついたものが並んでいます。
「奥は昔の机ですね。」
そして真ん中のペダルのあるものの上には、写真が飾られています。その写真にはキャプションが。
「奥は昔の机ですね。」
そして真ん中のペダルのあるものの上には、写真が飾られています。その写真にはキャプションが。
 中には、お宝が眠っていた。 |
?…「いとこの裕ちゃん(古関裕而)と」…!!
ご主人に尋ねると、
「ああ、奥(の女性)は、私の祖母です。」
ご主人に尋ねると、
「ああ、奥(の女性)は、私の祖母です。」
 古関裕而(手前)と、この家のご主人のおばあ様。いとこ、という事は… |
何と、福島県が生んだ偉大な作曲家で、去年ドラマのモデルにもなった古関裕而さんの、親戚の家だったのです!!!ご本人の写真も飾ってあります。という事は、おばあさまと写っていた写真の…
 おお、古関裕而さんの写真が…。このオルガンは…? |
オルガンが、現存していたのです!古関裕而が弾いた事のあるオルガンです。
「良かったら、弾いてみますか?」
良いんですか????勿論です!
「良かったら、弾いてみますか?」
良いんですか????勿論です!
 古関裕而が弾いた事のあるオルガンでした!! |
テレビで放送した通り、番組のテーマソングのメロディラインをちらっと弾かせて頂きました。
「オルガンは和音の方が、響きが好いんですよ。」
「オルガンは和音の方が、響きが好いんですよ。」
 ちょっとした汚れも、歴史を感じさせる。 |
ただ私には和音を奏でるまでの才能が無いので、取りあえず、ドミソ・ドファラ・シレソあたりの和音を押してみると、確かに音の厚みと拡がりが素晴らしく、重厚な音色が蔵に響き渡ります。
では隣のハンドルのある箱は……?
「蓄音機です。」
では隣のハンドルのある箱は……?
「蓄音機です。」
 上のボタンを引いたり押したりして音色を変える(西会津町でも見ましたね)。 |
蓋を開けると、懐かしのレコードがターンテーブルの上に載っています。ただ、昔の写真でよく見るようなラッパ状のスピーカーがありませんが…。
「これは、下の部分で共鳴するように出来ているんです。」
「これは、下の部分で共鳴するように出来ているんです。」
 おお、蓄音機だ!でもスピーカーはどこ? |
なんと内蔵型に進化していた頃のもののようです。
「音は出るんですよ。」
右のハンドルがゼンマイになっていて、ぎりぎりと回して針を乗せます。…音が出ました!が、ちょっと回転が遅いよう。
「回しが足りなかったかな…。」
ご主人が更に巻いて針を乗せなおしますが…回転数は上がりません。
「音は出るんですよ。」
右のハンドルがゼンマイになっていて、ぎりぎりと回して針を乗せます。…音が出ました!が、ちょっと回転が遅いよう。
「回しが足りなかったかな…。」
ご主人が更に巻いて針を乗せなおしますが…回転数は上がりません。
 ネットで調べてみたら1918年頃のアメリカ・コロンビア社製のもののようだ。 |
「ああ、ゼンマイが駄目になっているかも知れませんね。」
いえいえ、大正か昭和初期と思われる蓄音機から出る音が聞けただけで、大満足です。
しかし蓄音機やオルガンが個人宅にあるなんて、相当のお金持ちの筈。
「うちは呉服店で、この蔵で店をやっていたんですよ。」
いえいえ、大正か昭和初期と思われる蓄音機から出る音が聞けただけで、大満足です。
しかし蓄音機やオルガンが個人宅にあるなんて、相当のお金持ちの筈。
「うちは呉服店で、この蔵で店をやっていたんですよ。」
 音は出たが、回転数は余り上がらず…。これも歴史だ。 |
奥の棚には「木村呉服店」と書かれた篭が残っています。
「オルガンや蓄音機の置いてある方が通りに面していて、そこで店を開いていました。」
確かにオルガンの背後にある木戸を押し上げると、ガラス戸越しに通りが見えます。
「オルガンや蓄音機の置いてある方が通りに面していて、そこで店を開いていました。」
確かにオルガンの背後にある木戸を押し上げると、ガラス戸越しに通りが見えます。
 蔵の棚には、「店服呉村木」の文字(右から読む)が…。 |
「うちは天保三年(1832年)創業で、この蔵は江戸時代に建てたものです。」
絹織物は鎖国をやめてからは一大輸出産業となり、川俣町産のものは質の高さでも国内有数で、大正時代には軽便鉄道が、昭和には国鉄が鉄路を伸ばし、羽二重を盛んに運び出したものです。
当時はさぞこの辺りも賑わっていた事でしょう。
「昔の賑やかだった頃の写真がありますよ。」
(1月13日のブログにつづく)
絹織物は鎖国をやめてからは一大輸出産業となり、川俣町産のものは質の高さでも国内有数で、大正時代には軽便鉄道が、昭和には国鉄が鉄路を伸ばし、羽二重を盛んに運び出したものです。
当時はさぞこの辺りも賑わっていた事でしょう。
「昔の賑やかだった頃の写真がありますよ。」
(1月13日のブログにつづく)
 蔵には生糸の価格表が…。店だった名残だ。 |
全文を読む